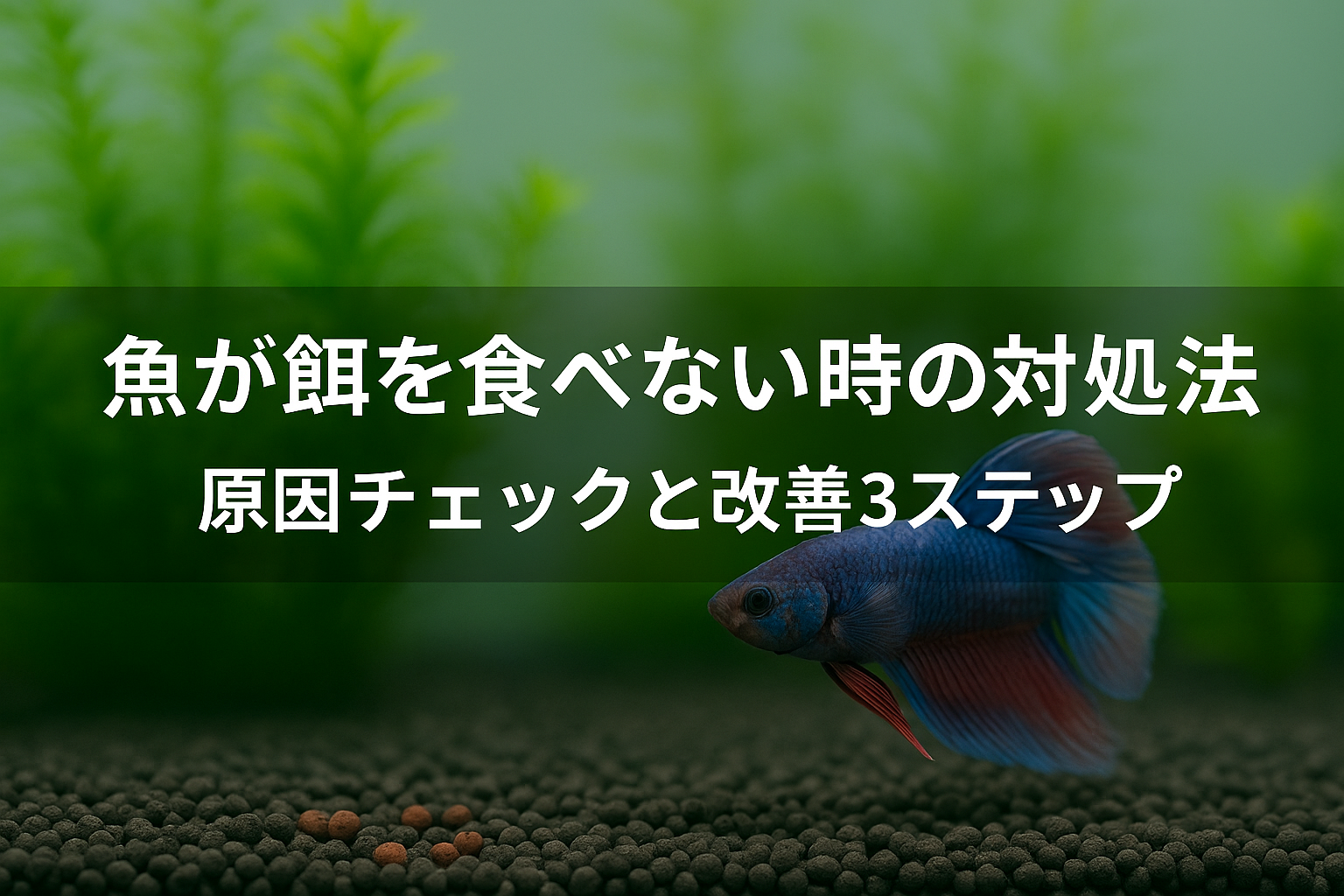「急に餌を食べなくなった」「数日ほとんど口を付けない」——水槽でよくある“拒食”。まずは水質・温度・ストレスの基本を整え、段階的に対処すれば多くは改善します。この記事では、安全に実践できる3つのアプローチと、やってはいけないNG、症状別の手がかりをまとめます。
まず最初の5分チェック(超重要)
- 温度:急変していないか(±1〜2℃/日以内)
- 溶存酸素:水面が揺れているか/エアレーションは十分か
- 水質:におい・白濁・油膜がないか
- 可能ならアンモニア/亜硝酸=0mg/Lを確認
- 外観:白点・充血・ヒレ裂け・腹部の張り・便の色を確認
- 導入直後:環境変化による一時的な拒食は数日で回復することも
強い症状(呼吸が速い/横転/出血など)があれば、まず水換え+強めのエア。
アプローチ1:環境を整える(食欲の土台づくり)
- 同温度で1/3換水(カルキ抜き必須)
- 水面撹拌を強化:吐出口を水面近くへ/エア追加
- 照明は6〜8時間に短縮
- 隠れ家(水草・流木・シェルター)を増やして視線を切る
- 給餌回数はいったん減らす(残餌→水質悪化を防止)
新規導入直後は2〜3日は様子見。群れ魚は同種を十分数で落ち着きやすい。
アプローチ2:餌の“形・匂い・タイミング”を変える
形状を変える
- 沈下性に変更/ふやかして柔らかく
- 粒を砕いて小さくする、ペースト状も可
匂いを強くする
- 冷凍赤虫・ブラインを少量トッピング
- 乾燥フードを飼育水で数分ふやかす
タイミング・方法を変える
- 消灯30–60分後の静かな時間に
- ピンセット給餌/流れに乗せて口元へ
- 絶食48–72時間でリセット(成魚・健康体に限る/幼魚不可)
いずれも1〜2分で食べ切る量に徹し、残餌は回収。
アプローチ3:ストレス・病気に備える(隔離/塩/薬の順)
隔離して落ち着かせる
まず、拒食ではなく**「横取りされて食べられていない」可能性を確認。
対策:①複数ポイント給餌**(左右2〜3か所) ②浮上用+沈下性で層を分ける ③ピンセットで目の前に落とす/消灯後に少量給餌。
改善しなければ、一時隔離して単独給餌(ヒーター・エア付きの別容器、2〜7日、完食主義)。本水槽内なら仕切り板/ブリーディングボックスでもOK。
短期塩浴(淡水魚の一部に有効)
- 目安:0.2〜0.3%(2〜3g/L) をゆっくり溶かす
- エビ・貝・水草・ナマズ系(コリドラス等)は避けるか0.1%以下・短時間
- 強めのエア必須。異変があれば中止し段階希釈
薬浴は「症状が明確」な時だけ
- 白点・カビ・細菌症状などに限定
- 表示用量・期間厳守/他薬と混用しない
- 生物ろ過が弱るため別容器が無難
やってはいけないNG
- とにかく餌を増やす(→水質悪化で悪循環)
- 急な温度変化
- 多薬併用・用量超過や根拠のない治療
- フィルター停止や過度な清掃でバクテリア全滅
- 拒食中の過密混泳や新規生体導入
症状別の手がかり(クイック表)
| 症状 | よくある原因 | まずやること |
|---|---|---|
| 朝だけ食べない | 夜間の酸素不足 | エア強化/吐出口を水面へ |
| 食べるが吐き出す | 粒が大きい・硬い・嗜好性不足 | 粒を小さく/ふやかす/冷凍赤虫少量 |
| 水面パクパク | 低酸素・高水温 | 水換え+強エア/温度を1〜2℃下げる |
| 体をこする・白点 | 寄生虫の可能性 | 早めに薬浴検討(表示厳守) |
| お腹ぺたんこ | 長期拒食・ストレス | 隔離・静穏・少量高嗜好フード |
| お腹パンパン | 消化不良・便秘 | 絶食48h→少量から再開 |
まとめ
- 拒食は環境>餌>治療の順でテコ入れ。
- 水換え・酸素・温度安定が“食欲スイッチ”。
- 餌は形・匂い・タイミングを変えて少量完食。
- 横取りの除外→短期隔離→塩→薬の順に、無理なく進めましょう。